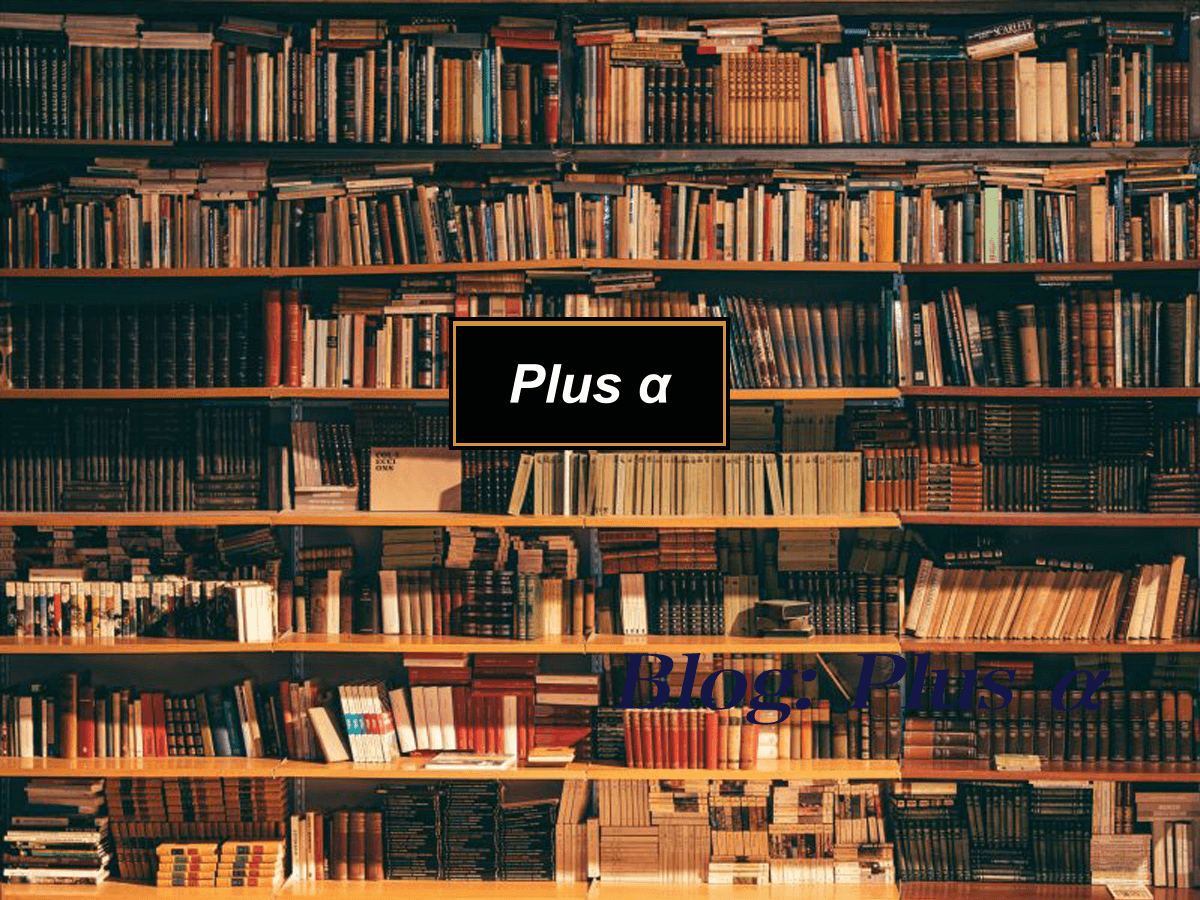白井弓子氏の『WOMBS (ウームズ)』(小学館・全5巻)という作品に関しては、過去に、しあわせな体験をさせてもらったことがある。版元である小学館主催の「第4巻・発刊記念トークイベント」の際にゲストとして呼ばれ、この作品をテーマに、対談させて頂く機会を得たのである。そのときの話は、当時、Facebookの公式ページで公開した。2013年の夏なので、私自身は『深紅の碑文』(早川書房)の最終仕上げに入っていた時期だった。
●コミックナタリーでの当時(2013年)の告知
http://natalie.mu/comic/news/96200
●上田のFacebook公式ページ
https://www.facebook.com/icthynavis/posts/367403726722468
2時間半ほどのイベントだった。その後、二次会でも白井氏の隣に座って、イベントでは喋れなかったことを少し話した。お互いの仕事に関することや、デジタル作画に関する話や、古い時代の戦車の整備に関する話など、いろいろと。
その後、本作の掲載誌であった「IKKI」(小学館)の休刊によって、本来ならば6巻で完結予定だったこの物語は、5巻に縮小する形で完結が決まった。そのため、この作品は、物語としては綺麗に完結しているのだが、当初予定されていた構想のいくつかを本筋から切り離しているようにも見える。本篇に盛り込めなかった部分は、いずれ、番外編の形でサイドストーリーとして描かれるのではないかと、個人的には期待している。
本作のあらすじに関しては、諸々のサイトにおける書評で既に詳細に記述されているので、ここでは繰り返さない。また、戦争の現実を生々しく描き出す視点や、過酷な状況下においてなお自己の意思を手放さずに進もうとする人々の心情なども、多くの読者によって語られる美点であろうが、本日ここでは触れない。この記事では、漫画作品という特質から見た、「画」そのものから意味を読み取る面白さについて、そのごく一部を挙げて言及してみたい。
【※以下の文章には、作品内容に触れる部分があるので、まだ作品をお読みになっていない方は、読む/読まないの選択を、慎重にお決めになって下さい。】
まず、第1巻冒頭である。
不思議な虫の生態が描かれているが、この場面では、この虫自体についての解説はない。しかし、ページを読み進めてゆくと、ある登場人物のセリフによって、この虫の名前が判明する。さらに巻が進むと、この虫が重要な役割を担っていたことがわかる。私は、初読のときからこの虫の存在が気になって仕方がなかったのだが、答えはきちんと用意されていた。
次に、同巻の別のページ。
セカンドの「人道的選択的制圧機(欺瞞的虐殺兵器)」に子供や群衆が引き寄せられている場面。そのコマの端に描かれているファーストの軍人とその直後に起きたこと、この軍人が誰なのかということは、物語がずっと先の巻まで進んだ時点で、「画」によって明瞭に明かされる(独白の言葉はかぶるが、状況を説明する台詞は一切ない) しかも、この瞬間は、転送兵開発の過去の秘密ともつながっているのだ。
第4巻。セカンドの新首都をAATで攻撃中、ある登場人物の眼前に「破壊されたアヒルのおもちゃに似たもの」が出現する場面がある。これについては最後まで具体的な答え(この場面に呼応するコマ)がないが、これによって、セカンドもファーストと同じく子育ての期間を持つ生物なのではないか、そして、この小道具が読者である我々にとって一瞬で子供のおもちゃを連想する形に描かれているということは、セカンドの生物としての形態が、ファーストと極めて似通っているのではないか、という推察を可能にするのである。(※註:セカンドは物語の最後まで姿を見せる機会はなく、その知性の質もかなり違うようだが)
これらは他の漫画家の作品でも見られる手法で、小説の場合は同様の措置を文章によって行うが、漫画は「画で語る」メディアなので、「画」そのものが伏線となり、読みどころのひとつとなっている。この手法から、白井氏は、作品全体の構造を決めやすい単行本書き下ろしや短篇作品だけでなく、連載作品においても、即興的な描き方ではなく、かなりの細部にわたって全体の構造を決めてから描き出すタイプの描き手ではないかと私は想像しているのだが、このあたりの詳細は、作家本人が、再び創作秘話などで語って下さる機会があれば歓迎したい。「画」によって伏線を積み重ねる手法は映画でも同様に使われるが、漫画は書物という特性上、すぐに前のページや別の巻に飛んで内容を確認しやすい。その早さ、手軽さを利用した魅力のひとつと言えるだろう。
(※映像作品も記録メディアに落とせばこれが可能になるが、書物よりは確認に手間がかかり、また、劇場用作品の場合、一般公開からディスク発売や配信開始までの期間は、作品を巻き戻して観ることができない。該当箇所を確認したければ、頭から見直す形になる)
もうひとつの特徴。
この作品では、「現実空間」と「テクノロジーが作り出す座標空間」さらに「座標空間と重なり合うニーバスの幻影」が三重構造になって提示されるが、このそれぞれの層を描くときの描画タッチを、白井氏はほとんど変えていない。読者は位相の違う空間の「画」が重なり合う描写や、物語の文脈によって、この各層間の移動を把握(体験)していくわけだが、この座標空間上に現実ではありえない光景が出現する瞬間や、現実と幻想が重なり合っていく描写、人間の精神がそれに引きずられて自己と世界との境界線を喪失していく過程の描写が、私には非常に快感であった。幻想系の映画や漫画では普通に使われる手法だが、本作全体を貫いている「飛ぶ」というイメージとの相乗効果が非常に高く、実に気持ちがいい。
漫画は「画」の表現込みで味わう創作物なので、物語の魅力に加えて、絵柄やデッサン力、画そのものが作り出す意味に、このような形で注目していくと面白い。
最後に、追記として、画ではなく、言葉において印象的だった部分をひとつ挙げておく。
転送兵として子宮を提供した女性たちは、ニーバスの細胞を移植されることを決して妊娠とは呼ばない。男性兵士からの視線に含まれる同一化された「妊娠」という言葉に対して、強い意思を持って逆らう。ある「女性兵」は言う。『私らは転送兵。母親じゃない!』と。
その一方で、ある「男性登場人物」は、成長途上のニーバスに向かって言うのである。『私こそが、お前の産みの親だ。』『私が親として命じる』と。
この逆転構造が何を示唆しているのか、その解釈は、それぞれの読み手にゆだねられるだろう。私は、なんと魅力的な見せ方かと感じた。