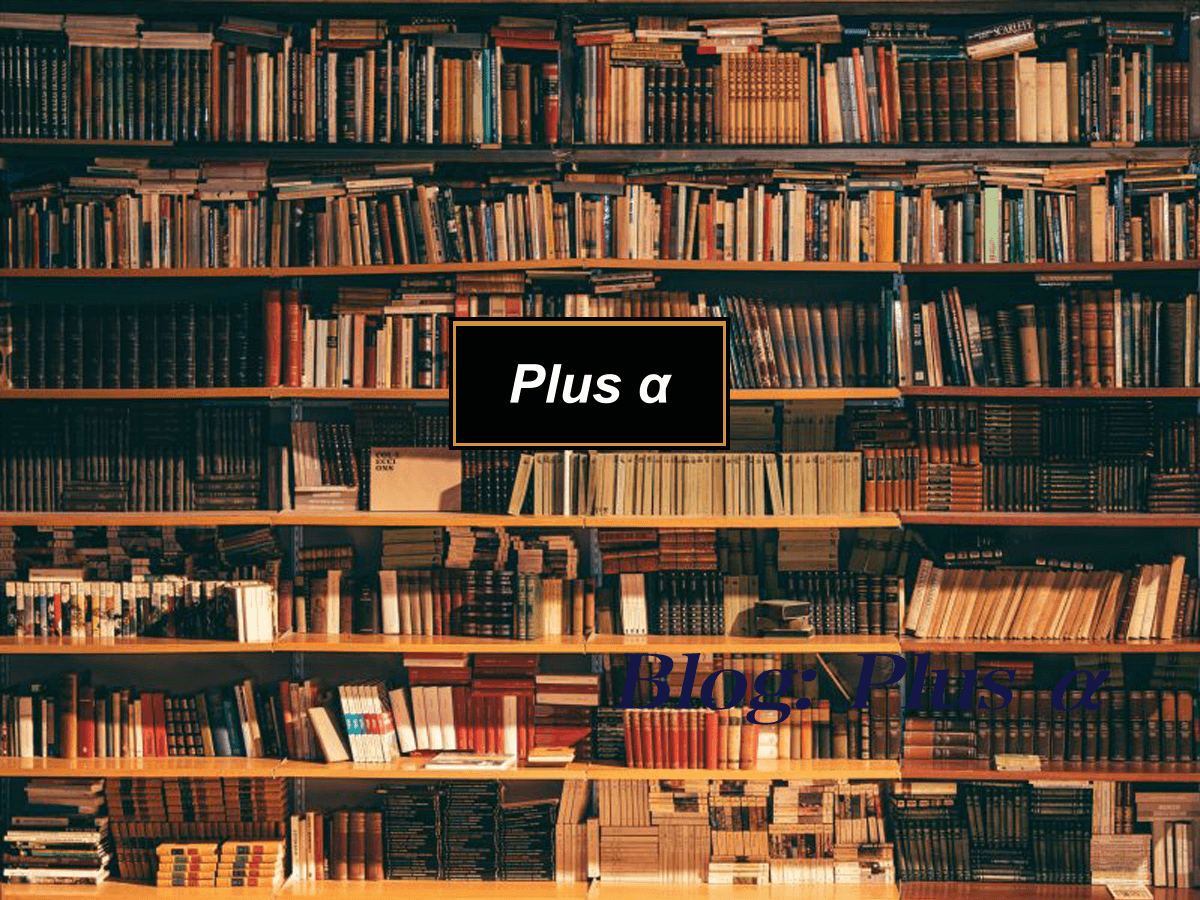前々から言及している通り、構想ノートの段階では架空の海洋惑星が舞台であった大長編SFは、早川書房へ企画を持ち込んだ段階で未来の地球の話に変更していた。各エピソードは構想ノート通りではなく、必要な要素のみ切り出し、単行本一冊分の物語としてまとめた。これが最終的に、『華竜の宮』として刊行されることとなった。
2000年代前半は、『活字SFで「宇宙」と「SF」の要素が重なると、一般の読者は読んでくれない(本の刊行自体が難しい)』と業界内で言う人もおり、実際、過去に自分の本を刊行したときにも当たらずとも遠からじという反応だったので、より多くの読者にアピールするには、架空の海洋惑星という舞台を捨て、地球の話にする必要があった。青澄とマキは構想ノートの段階から存在しており、この時点で既に「異民族・異種族間の調停者」という役割を与えられていたので、これを地球の話にするには、外交官の話に置き換えるのが最もよいだろうと判断した。
たまたま、その時期、新聞広告で『幻の終戦工作 ピース・フィーラーズ 1945夏』(竹内修司/文春新書 2005年)という本を見かけ、ピンときたので読んでみたら、これが大いに参考になった。著者インタビューで何度か言及しているが、これは第二次世界大戦末期に、日本になるべく有利な条件で終戦へ導くための和平工作に奔走した、外交官や駐在武官の活躍を記したノンフィクションである。この工作は失敗に終わるのだが、もし成功していたら、日本への原爆投下はなかったのではないかとも言われているらしい。推理小説作家の松本清張は、この史実を題材に『球形の荒野』という作品を発表している。
史実を参考に作品の構造を考える方法はとても役に立ち、『華竜の宮』のあとに執筆した『深紅の碑文』でも、一部、近現代史をベースにした(※歴史好きの読者は、どの時代の誰の話がベースになっているのか、すぐに気づいたようだ)
さて、海洋惑星ではなく地球の話にするには、地球の環境下で大規模海面上昇を引き起こす必要があった。それを発生させるためのヒントとなったのが、『日本列島は沈没するか?』(西村一、藤崎慎吾、松浦晋也(著)/早川書房 2006年)という本と、宇宙作家クラブでの地球惑星科学に関する勉強会だった。
この勉強会へ地球惑星科学の専門家を招いて下さったのが、サイエンス・ライターの鹿野司さんであった。
宇宙作家クラブの勉強会では、書籍でしか知らなかった地球内部の熱対流のイメージが具体的に鮮明となり、とても参考になった。こういう部分は、やはり専門家に話を聞かなければ、非専門家にはなかなかイメージしにくい部分だ。あまりに面白かったので、その部分は作品のプロローグで本文に反映させた。
また、『日本列島は沈没するか?』は、大規模海面上昇の仕組みを考える際に、非常に参考になった。絶版になっていることが、とても惜しまれる本である。当時私は「地球・海洋SFファンクラブ」を通して、JAMSTECの西村一さん(いまは退職しておられます)と既に交流があり、「地球外部から水を足さない方法で大規模海面上昇を起こしたいのだが、その方法としてはどのようなものが可能か?」と、メールでお訊ねしたのだった。直近のアニメ作品で、水を大量に含んだ巨大彗星が衝突することで地球の海面上昇が起きる設定の物語があったので、それとは別の方法を採用したかったのだ。CO2による地球温暖化だけでは、自分が想定するレベルの海面上昇が得られないことがわかっていたからである。
『日本列島は沈没するか?』には、「地球内部のマントルに含まれている水分(岩石と化学的に結合している)をすべて海へ戻せたとしたら、全地球規模で600メートルの海面上昇が起きる」というくだりがあった。これは非常に興味をそそられる話で、私が知りたかったのは、このマントル内に含まれる水をすべて地表へ戻すにはどうすればいいのか、ということだった。
西村さんとメールをやりとりを重ねるうちに、「すべての水を戻すのは無理」とか「『マントル内に水は存在していない』と考える研究者もいる」等々の話が出てきて、どんどん、地球惑星科学関係の相談が深まっていき、そうなると、地球規模の大災害の話を避けて通れなくなってきた。大災害関係の資料は、当時でもまだ目を通すのが精神的にしんどかったのだが、人類が全滅するぐらい大規模な災害なら、スケールが大きいので逆に実感が湧きにくい。この「実感が湧きにくい感覚」こそが、自分の作品に登場する人々の行動を決めるのではないかという予感もあり、最終的には積極的に扱うことにした。
大災害は来るのか、来ないのか、来るとしたらいつなのか。
これもまた、読者が感じる生々しい感覚と共通するものであり、当時はいまほど巨大地震や大災害が警戒されていなかったのだが、強く意識して描くべきだと考えたのだった。
(29)【著者記録: 2003-2023】『華竜の宮』刊行へ向けて (6)