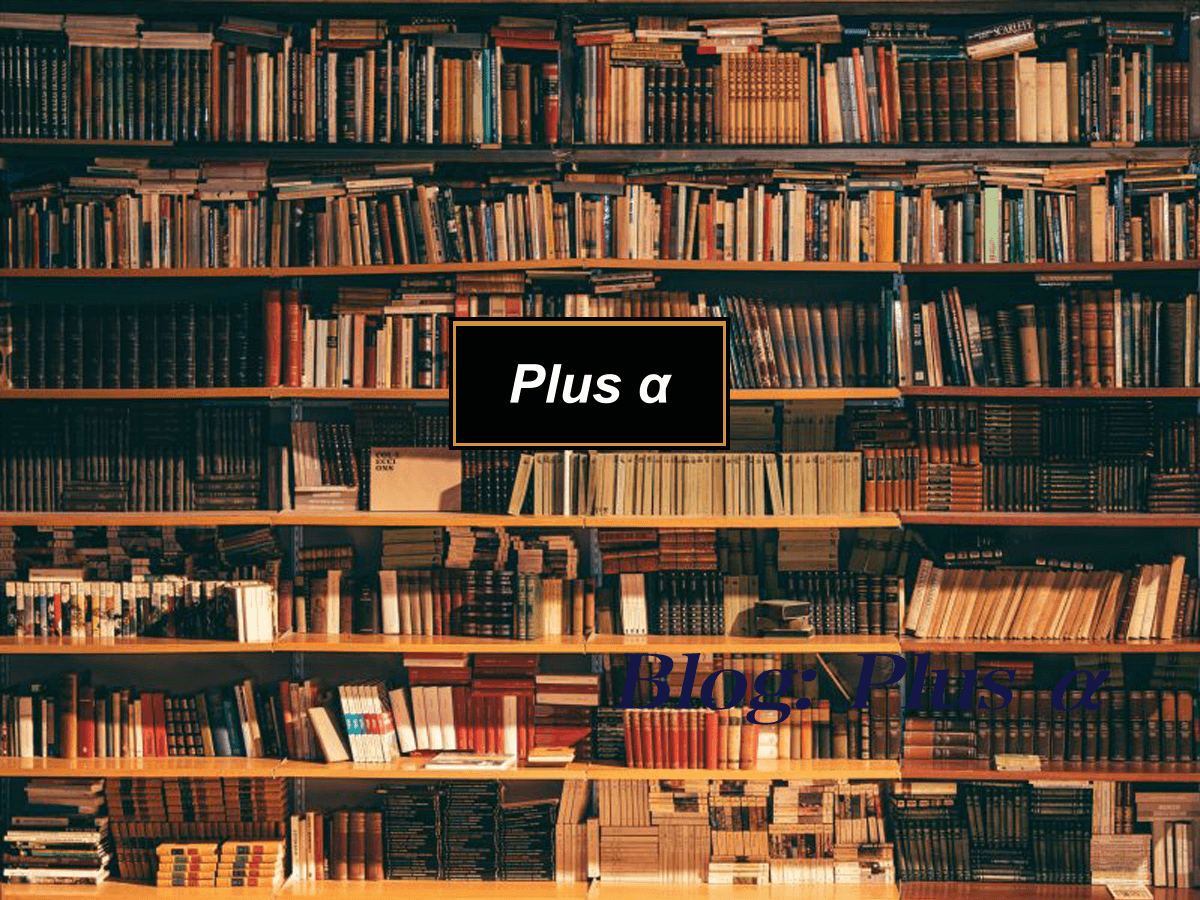『深紅の碑文』以降の著作の刊行順次が、「百目シリーズ」→『薫香のカナピウム』→短編集『夢みる葦笛』→『破滅の王』となっているので、読者から見ると、著者が、ある時点から突然歴史小説へ方向転換したように見えるかもしれない。だが、前回記したように、双葉社の担当編集者から執筆を依頼されたのは2011年夏までの段階、『華竜の宮』が日本SF大賞を受賞するよりも前なのだ。
これまで説明してきた事情から、私は2011年の時点で、既に、SFと歴史小説の仕事を同時進行でこなす書き手になっていた。その成果が、やっと、本格的な歴史小説の書籍として目に見えるようになったのが、2017年の『破滅の王』なのである。
(これより4年前の2013年には、戦時上海三部作の前段階の作品となる「上海フランス租界祁斉路三二○号」を「小説宝石 2013」に寄稿している)
双葉社の編集者からは、「SF以外の作品をお願いします」と依頼されていた。ハードボイルドか冒険小説を書いてほしいのだという。私はこれに対して「自分はミステリの新人賞出身作家ではないし、なおかつ女性作家なので、そういったものを書いても、その分野で作品が評価されることはまず有り得ない。それよりも歴史小説を書かせてほしい。歴史の枠組みの中で冒険小説的なニュアンスを見せたほうが面白い作品になるだろうし、私の作品を届けるべき読者層に、確実に作品が届くはずだ」と伝えて、納得してもらった。
もともと、歴史に興味を持っていたことは、これまでのエッセイの中でも述べた通りである。そして、かつて(10代の頃)の私にとっての冒険小説の入口は、ジャック・ヒギンズやアリステア・マクリーンだった。第二次世界大戦下で戦う男たちの生き様と死に様を描いた作家の作品群。だから、冒険小説といえば歴史や特定の時代とリンクしているものというイメージが、私の中には大前提としてあった。それと似た雰囲気を持つ物語舞台のほうが、自分が初めて手がける歴史小説としては書きやすいはずだと考えた。物語の基本的な形をよくわかっているのだから、そこから創意工夫できるだろうと。
「上海租界を舞台にするのはどうですか」と切り出したのは、私ではなく、担当編集者のほうである。私は 1980年代に幾つもつくられた日中近代史を扱ったフィクション群(映画なども含めて)にリアルタイムで触れてきた世代なので、一般的な上海租界に関する常識は持っていたが、それを自分で小説にできるほどの知識はなかった。そこで、あらためて戦時上海(1930~1940年代)について調べ始めた。さまざざまな国の民族が集まっている租界は、よくよく考えてみると、オーシャンクロニクル・シリーズに登場する海上都市と雰囲気が似ており、いまの自分なら何か面白いものにできそうだなと感じたのだ。
中国は文革後に情報公開が盛んだった時代があり(1980年代)、このときに、それまで知られていなかった史料が、たくさん世に出てきた。これが1990年代以降の研究成果として、日本でも論文や専門書の形でまとまったおかげで、私のような非専門家でも目を通すことが可能になった。
1980年代以前に活躍していた作家は、戦時上海について書こうとするとき、戦中の本人の体験をもとにするか、80年代よりも前の資料に頼るしかなかった。だが、2010年代以降に執筆する書き手には、新しい資料から導き出される新しい視野を、物語に取り込むことができるようになったのだ。
これまで様々な作家によって書かれてきた時代であっても、繰り返し、新しく創作がなされるべき理由と意味はここにある。日中近代史にはまだ掘り起こされていない史料がたくさんあり、それが開示されるごとに、新しい視点でフィクションをつくり出せる余地が生まれる。
「いま、なぜこの時代を?」という問いには、日中近代史だけに限っても「フィクションの中で書かれるべき出来事が、まだまだ掘り起こされてないから」と答えるしかない。あれも、これも、まだ誰も書いていない。見つけ次第、それに気づいた作家が書くべきなのだ。
歴史小説の執筆は、歴史の専門家の研究成果があって初めて可能になる。現在、大学で研究を続ける現役の歴史学者の努力と洞察なくして、フィクションで歴史を扱う方法は存在し得ないと思う。個々の作家は必ずしも歴史の専門家ではないので、資料の調査の範囲は、自分の力の及ぶところまでで構わないだろう。また、あえてそういったものを無視して書く方法もある(歴史改変小説とか、歴史伝奇小説とか)
だが、どんな場合でも、専門家の仕事に目を通して敬意を払い続けることが、フィクションという虚構を利用して歴史を扱う作家に求められる誠実さではないかと、私自身は考えている。
(32)【著者記録: 2003-2023】歴史小説への道 (1)