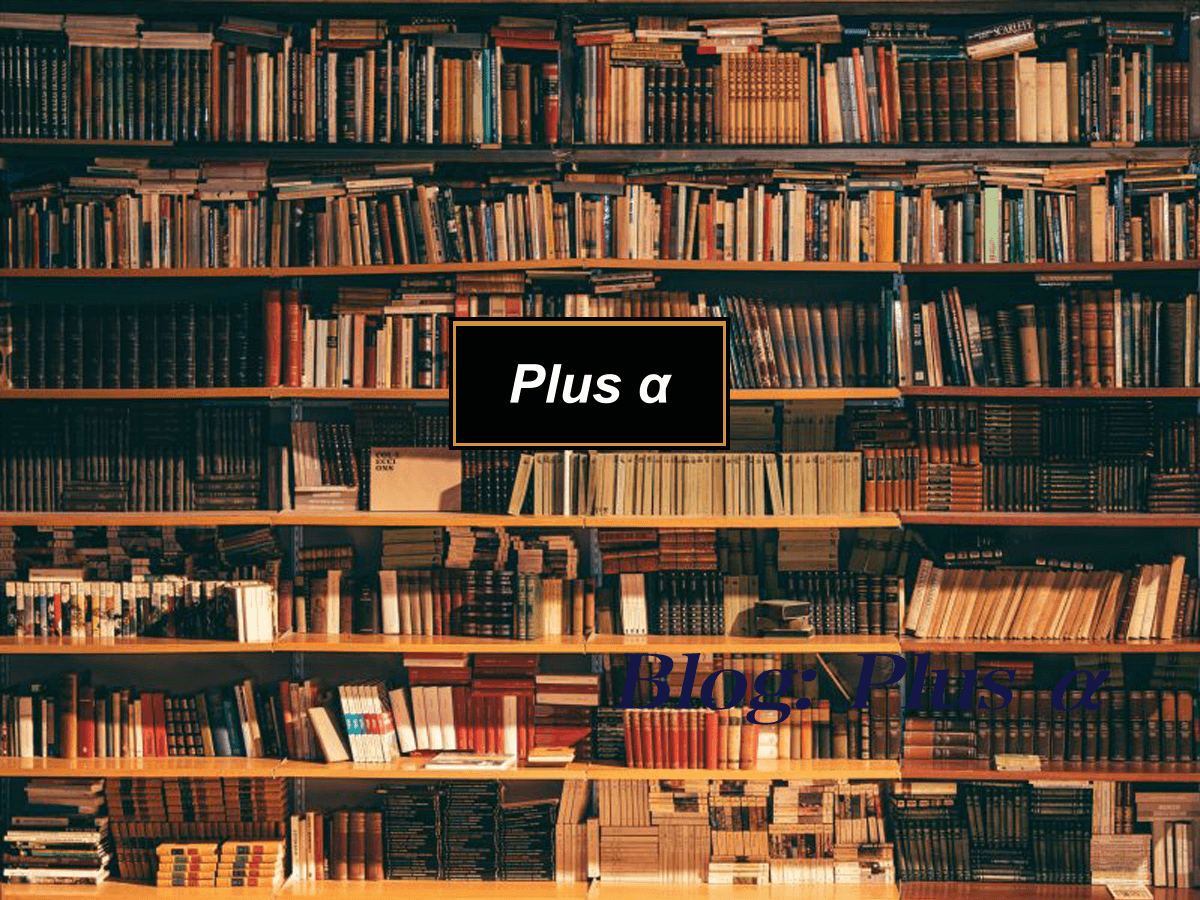感想を投稿する順序が逆になったが、夏頃、刊行直後に、中国史SF短篇集『移動迷宮』(中央公論新社)を読んだ。大恵和実さん、上原かおりさん、大久保洋子さん、立原透耶さん、林久之さん――と、古くから中国文学に造詣の深い方々が、新たに中国SF翻訳の現場に加わった大恵和実さんの企画のもとに集まった、最高の歴史SFアンソロジーだ。
昨日感想を投稿した、宝樹『時の王』(早川書房)の翻訳にあたられた稲村文吾さん、阿井幸作さんなど、以前から中国文学を翻訳してきた方々のおかげで、私たち日本の読者は、世界的に注目されている中国SFを、かなり早い速度で、次々と邦訳で読める状態になっている。SFの翻訳は、専門用語や専門の概念が必要になるため、中国語を翻訳できる能力があるだけでは難しい作業になるそうだ。しかし、『折りたたみ北京 現代中国SFアンソロジー』/ 『月の光 現代中国SFアンソロジー』 (ともに、早川書房/新☆ハヤカワ・SF・シリーズ) 、『時のきざはし 現代中華SF傑作選』(新紀元社)と、これまでのアンソロジーでも、中原尚哉さん、 大谷真弓さん、鳴庭真人さん、古沢嘉通さん等々、名前を挙げ尽くせないほど多くの翻訳家の方々が積極的に関わって下さったおかげで、いま日本では、台湾のSF作家の作品も含めて、たくさんの中国人作家の短編SFを読めるようになっている。本当に、ありがたいことだ。

聞くところによると、これでも日本には、まだ、ほんのひとにぎりの中国SFが紹介されているに過ぎないという。たとえば、ハードSF系の短編はまだほとんど訳されていない。サイバーパンク系の長編も、入ってきているのは、陳楸帆の『荒潮』(早川書房/新☆ハヤカワ・SF・シリーズ)ぐらいだ。いったい、どれぐらいの中国SFが、まだ日本に届かず知られていない状態なのだろうか。それは、いつ届くのだろうか。あるいは、どこかで翻訳の機会が、一段落ついてしまうのだろうか。
日本から中国へのSF作品の翻訳頻度も、どこまで継続されるのか気になるところだ。さまざまな事情から、これが滞る可能性が考えられるからである。
さて、『移動迷宮』の話に戻る。
この本には、他のアンソロジーとは違う、大きな特徴がひとつある。編者である大恵和実さんの意図により、なんらかの形で中国史を扱った短編SFばかりが収録されているのだ。歴史SFアンソロジー、あるいは中国史SFアンソロジー、と、ここでは便宜上呼んでおく。
中国史に関しては、日本の読者は、先行する著名な作品群によって馴染み深い時代もあれば、授業で学ばないことから予備知識が皆無という時代もある。ところが不思議なことに、中国史SFは、どれを読んでも(こちらに基礎的な知識が乏しくても)なぜか、とても面白い。これは、そんな面白い歴史SFが7本も詰まった、素晴らしいアンソロジーだ。
このレベルの中国史SFアンソロジーが、年に一冊ぐらいのペースで毎年刊行されていったら、私は、ちょっと躍り出してしまうほどうれしい(翻訳する側は大変だろうが……)
きっと多くの歴史SFファンが、それをきっかけに、これまであまり調べていなかった時代について、もっと調べてみようという気にもなるだろう。ありがたいことに、いまはスマホを片手に読み進めれば、知らない言葉が出てきても少しは調べられる。この作業は結構楽しい。「これは史実か、虚構か……?」と読みながら判断に迷ったときなど、一瞬で調べられる。物語の舞台となった場所の画像なども観られる。いい時代になったものです
私は巻頭の「孔子、泰山に登る」(飛氘・著)から深く感動してしまい、まさか、この歳になって孔子の話に感動して、じんわりくるとは思わなかった。自分が歳をとったせいだろうか。そして、その老いたる老子の話を書いたこの作者が、1983年生まれという、自分よりも19歳も若い作家であることも、とても興味深く感じるのである。若いといっても飛氘の筆致は堂々たるもので、その澄んだ静けさを湛えた作家の感性には、さまざまに教えられた気がした。
そして、日本の読者からの評判がとてもよいのが、「南方に嘉蘇あり」(馬伯庸・著)だ。茶の歴史をコーヒーに置き換えたこの作品は、背景になる中国史に詳しくなくても、なぜか非常に面白い。たとえば同じことを日本史でやって、海外の人が読んだときに同じ面白さは維持できるのだろうか? 面白くするには、どのような手法が有効だろうか? そのようなことを、さまざまに考えさせられる作品だ。それにしても、本当によくできている。なんで、こんなに面白いのだろう。
その他、「陥落の前に」(程婧波・著)、「移動迷宮 The Maze Runner」(飛氘・著)、「広寒生のあるいは短き一生」(梁清散・著)、「時の祝福」(宝樹・著)、「一九三八年上海の記憶(韓松・著)、「永夏の夢」(夏笳・著)が収録されており、それぞれが、美しくも妖しい鮮烈なイメージに牽引される作品だったり、胸が痛くなるような切ない物語だったり、人間の業の深さをのぞき込むような作品だったり、歴史と人間というものの関わりが、さまざまな姿で立ち現れてくる。飽きない。何度も書くが、このレベルの中国史SFアンソロジーを年に一冊ぐらいのペースで読み続けられるなら、中国史SF好きにとっては至福でありますよ……。
最後に一作、韓松の「一九三八年上海の記憶」について、分けて言及しておきたい。
編者の大恵和実さんは、中国史SFアンソロジーを編む企画を立てたときから、必ず一本は、近代史を題材にした作品を入れると決めていたそうだ。とても素晴らしい判断だと思う。
韓松のこの作品は、現実の日中戦争の時代を背景に、虚構が入り交じる歴史(次々と分岐しているらしい歴史)が語られる異色作だ。
(現実の歴史では1937年に盧溝橋事件、第二次上海事変。1941年の太平洋戦争勃発と同時に、日本軍が上海を全面的に占領して、上海が「孤島化」する。このとき、上海租界に住んでいた欧米人が周辺の強制収容所へ送り込まれるが、その中に、のちにSF作家となる、子供時代のJ・G・バラードがいた。バラードの生い立ちについては、『太陽の帝国』や彼の自伝をご参照下さい)
ベースになっている近代史を知っていると、作中の何がどんな意味を示しているのか、その読解(必ずしも、ひとつの意味を示しているわけではないはず)に、とても興味をかきたてられるだろう。韓松の作風は、一筋縄ではいかない複雑な構造を持っていることで有名だが、日本でも既に多くのファンがいて、邦訳を待てない人たちが、どんどん中国語の原著を読み進めている状態だ。それぐらい、日本の中国SFファンから、多くの邦訳を待ち望まれている作家である。私は、自分自身が、この8年間ほど、戦時下の上海を日本側からの視点(主に戦史の側面)から見た作品を書き続けているので、韓松のこの作品には本当に興奮してしまった。この時代に、この作品と巡り会えたことの意味を深く考えざるを得ない。貴重な体験をさせてもらった。
この本の最後には、中国の歴史SFと日本の歴史SFの比較についての、編者による分析もある。たぶん、SF史上初の試みだろう。そのような資料的な価値も高い一冊だ。